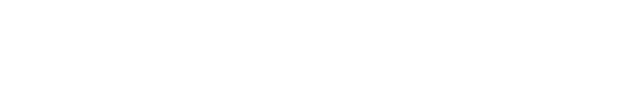もの忘れ外来
「最近、もの忘れが増えた気がする…」「もしかして、認知症かも…」
もし、あなた自身や大切なご家族にこのようなご不安があるなら、当院のもの忘れ外来へご相談ください。もの忘れをはじめ、気になる症状について専門的に診察し、分かりやすくご説明します。
もの忘れ外来とは
もの忘れ外来は、もの忘れを主な症状とされる方や、そのごご家族が安心して診察を受けられるよう開設しました。患者さんの生活状況を丁寧にお伺いするため、完全予約制で時間を確保して対応しています。
認知症の症状は、もの忘れから始まることが多いですが、それだけではありません。「外出がおっくうで、一日中ぼーっとしている」「今まで得意だった料理や片付けが、段取り良くできなくなった」といった変化も、大切なサインかもしれません。
「いつもと何かが違うな」と感じたら、どんなに些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
もの忘れ外来の目的
- 「もの忘れ」の状態を正しく診断し、分かりやすくご説明します。
- 認知症に関する正しい情報を社会に提供します。
もの忘れ外来の対象
- もの忘れなどの症状により、日常生活でお困りごとや不安を抱えている方、そのご家族や支援者の方。
開設時間
毎週火曜日 9:00~12:30
毎週金曜日 13:30~17:30
もの忘れ外来のスケジュール
当院では、もの忘れが心配なご本人やご家族に対し、まず看護師が時間をかけて丁寧にお話を伺います。普段の生活の様子を詳しく把握することが、もの忘れ外来の診察では非常に重要です。そのため、同居されているご家族がいらっしゃる場合は、できるだけご一緒にお越しください。
問診後、いくつか認知機能検査を行い、その結果を踏まえて医師が診察します。必要に応じて血液検査やMRI検査も実施します。
- 問診と検査 現在ののお困りの症状を伺い、脳の働きをみる3つの検査を行います。医師による診察を合わせて行い、身体の異常がないかを調べるために心電図、血液検査、尿検査を行います。
- MRI検査 脳の異常がないかを調べるためにMRI検査を行います。連携している病院でMRI検査が行えるように、受付でご予約をお取りします。
- 診察・結果説明 血液検査やMRIの検査の結果が届いたら、当院へお越しいただき、結果の説明を行います。必要であればお薬を処方します。
- 診察 お薬を開始したはじめは、副作用(気持ちが悪かったり、食欲がなくなるなど)の症状がみられることがあります。当院ではお薬を開始してから2週間後にご来院いただき、お薬の効果や体調の確認を行っています。お薬を始めてから体調の変化がありましたら、次回の予約を待たずにご連絡ください。ご連絡をお待ちしております。
受診にあたって
認知症の診断には、ご本人とご家族からの情報が非常に大切です。ご本人のお話はもちろん、ご家族から見た普段の様子など、日々の生活の中での「困ったこと」「気になること」が診断の手がかりとなりますので、詳しくお聞かせください。
もの忘れ外来後の診療
検査や問診の結果から、現在の状態について詳しくご説明し、今後の生活について一緒に考えていきます。
- 認知症と診断され、治療が必要な場合は、当院で治療を行います。
軽度認知障害(MCI)と診断された場合の治療について
軽度認知障害(MCI)は、認知症の一歩手前の状態とされ、将来的に認知症へ移行する可能性のある状態です。しかし、MCIの方全員が認知症になるわけではありません。当院では、MCIと診断された方に対し、以下のようなアプローチでサポートします。
- 定期的な経過観察:MCIは一定の確率で認知症に移行する可能性があるため、半年後または1年後に再度認知機能検査を行い、慎重に経過を観察します。 早期の変化を捉え、適切な対応を検討します。
- 抗アミロイドβ抗体薬に関する情報提供と紹介: 新しい治療選択肢として注目されている抗アミロイドβ抗体薬の治療について情報提供いたします。この治療は特定の条件下でのみ適用され、専門的な施設での実施が必要です。必要であれば、治療可能な医療機関へご紹介いたします。
- 非薬物療法と生活サポート::MCIであっても、日常生活で困りごとや不安がある場合は、薬物治療に加えて、生活習慣の改善(バランスの取れた食事、適度な運動)、知的活動の促進、社会参加の奨励など、非薬物療法を通じて認知機能の維持・改善を目指します。 看護師がお困りごとを伺い、必要に応じてケアマネジャーと連携して介護保険サービスの調整なども行い、日常生活を総合的にサポートします。
認知症と診断された方へ
認知症とは、様々な病気によって脳の働き(記憶力や物事を一人で行う力など)が低下し、日常生活に影響が出ている状態をいいます。
認知症と診断されたからといって、突然に何もわからなくなったり、今までできていたことが突然できなくなることはありません。同じ年齢の人よりも少しだけ早く、もの忘れが多かったり、物事を行うことに少し時間がかかったりするようになっただけです。
私たちは、患者様が安心して、自分らしく生活できるようにサポートしていきます。心配なことや聞きたいことがあればいつでもご相談ください。
認知症の進行を遅らせるポイント
- 今まで行っていたこと(趣味や日課)を続ける 長く続けていたことは、認知症になっても忘れずに続けられます。楽しみながら行いましょう。
- 友達や家族とたくさん交流する いろんな人と話したり交流することは、脳の活性化や心の安定につながります。家に閉じこもらずに、いろんな人と話しましょう。
- 定期的に体を動かす機会を作る 体の健康は脳の健康にもつながります。体操教室に通うなど定期的に運動をしましょう。デイサービスは運動をしたり、同じ年齢の方との交流することもできます。
- 困ったときは周りの人に頼る。一人で抱え込まない 悩んで落ち込んでしまうことがあるかもしれません。そんな時は自分だけで抱え込まずに誰かに相談してください。
- お薬をしっかり飲んで、体調管理をする 今まで処方されているお薬をしっかり飲んで、体調が悪くならないようにすることも大切です。心配なことがあれば医師に相談してください。
もの忘れ外来担当看護師よりご挨拶
【認知症看護認定看護師:鈴木 恭子 (すずき きょうこ)】
私は、病院勤務、地域包括支援センターでの勤務を経て、「もっと患者様の人生に歩み寄って看護師としての役割を果たしたい」「患者様と看護師という関係だけでなく、人と人として誠意を持って向き合いたい」という思いが強くなりました。
認知症看護認定看護師として勤務する中で、認知症に対する誤った考えを持つ人が多くいると感じました。そして、私自身もそうでした。
「認知症=ケアを受ける人」そう思っていた部分がありました。
しかし、たくさんの当事者やご家族、支援者の方と関わらせていただき、私が認知症の方から、たくさんのことを教えてもらったり、元気をもらう出来事がたくさんありました。
認知症は、身近な病です。私だってそうなるかもしれません。「血圧が高い」のと一緒です。そうなることを予防したり、なったとしても当たり前に生活できる。そんな社会にしていきたい。そう思っています。
正しく知れば何も怖くない。認知症やもの忘れに関することで今不安に思っている方の支えになりたい。
私がたくさん当事者の方々に教えていただいたことを発信していきたい。その思いのもと、もの忘れ外来を開設しました。
当クリニックでは、看護師が積極的に患者様やご家族とお話をし、さまざまな健康や生活のお悩みをお聞きします。患者様お一人おひとりの生き方に合わせ、病気を抱えながらも希望をもって自分らしく生活が続けられるよう、精一杯サポートさせていただきたいと思っています。
私は患者様とお話することが大好きです。些細な質問でも雑談でも構いませんので、ぜひ、気軽にお声がけください。